活動紹介
2025年度 関東支部例会
日程:6月1日(日)第1回研究発表会
6月28日(土)講演会・第2回研究発表会
場所・開催方法:
① 6月1日(日)Zoomによるオンライン開催
② 6月28日(土)対面開催
場所:城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス 【3号棟】 2階 3202教室
(半蔵門線「半蔵門」駅4分、有楽町線「麹町」駅5分、南北線・半蔵門線・有楽町線「永田町」駅5分 )
① ②ともに、参加を希望される方は5月29日(木)までに ※こちらのフォームから申込みをしてください。
① 6月1日(日)のオンライン参加の方法については前日までにメールでご案内します。
内容:
① 6月1日(日)14:00〜15:30
◎第1回研究発表会
座長:小野由美子(東京家政学院大学)
1.石島恵美子(茨城大学)・橋長真紀子(札幌学院大学)
家庭科における食と環境の教育プログラムの検討―スイスの食育カリキュラムを参考に―
2.柿沼由佳(全国消費生活相談員協会)
偽誤情報を取り巻く消費者教育について考える
3.高橋義明(明海大学)
飲食店におけるフードロスと消費者行動
② 6月28日(土)14:00〜16:40
◎講演会 14:00〜15:30
テーマ:教育振興基本計画におけるウェルビーイングの位置付けと日本の教育の今後について
<講師>廣田 貢 氏
文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部計画課長(前 総合教育政策局政策課企画官)
<コーディネーター>高橋 義明 氏
明海大学経済学部 教授
現行の第4次教育振興基本計画(2023年閣議決定)では「持続可能な社会の創り手の育成」とともに
「日本に根差したウェルビーイングの向上」が2つの柱として掲げられ、
「ウェルビーイング」がキーワードとなっています。
そのウェルビーイングも子供たちのウェルビーイングの向上に止まらず、
子どものウェルビーイングを高めるためには教師をはじめとする学校全体のウェルビーイングが重要であること、
また子供たち一人一人のウェルビーイングが、
家庭や地域、社会に広がっていき、その広がりが多様な個人を支え、
将来にわたって世代を超えて循環していくという姿の実現が求められること、
と社会全体のウェルビーイングの向上が目指されています。
そこで今回はその取りまとめに尽力された文部科学省の廣田貢氏を講師にお迎えし、
ウェルビーイングが教育振興基本計画に位置付けれた経緯、日本に根差したウェルビーイングの意味や教育に与える影響などについて伺い、
日本における今後の消費者市民教育のあり方について議論する機会にできればと考えております。
議論を深めるため、参加ができない方も含めて申込フォーム等で事前に質問をお送りください。
◎第2回研究発表会 15:40〜16:40
座長:神山久美(山梨大学)
4.丸山智彰(東京大学教育学部附属中等教育学校)
「広告」を題材とした高等学校家庭科の消費者教育―レポート共有と対話を通して―
5.阿部信太郎(城西国際大学)
フィンテックに関わる探究学習試論
2025年度 関東支部総会・シンポジウム
日程:2024年12月24日(火)・講演会 14:00~15:30
※支部会員対象/受付開始13:50
・総 会 15:45~16:30
場所:城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス 【3号棟】 4階 3414教室
(半蔵門線「半蔵門」駅4分、有楽町線「麹町」駅5分、南北線・半蔵門線・有楽町線「永田町」駅5分 )
講演:<テーマ>OECD ラーニング・コンパス2030から消費者市民教育の今後を考える
<講師>田熊 美保 氏
OECD教育・スキル局Future of Education and Skill 2030 プロジェクトリーダー
<コーディネーター>高橋 義明 氏
明海大学経済学部 教授
ラーニング・コンパス2030は経済協力開発機構(OECD)が今後の教育の姿として関係者と対話を重ね、「2030年に望まれる社会のビジョン」と「そのビジョンを実現する主体として求められる生徒像とその資質・能力」を2019年に取りまとめた報告書です。
ラーニング・コンパス2030では2030年の目標として個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイング双方の向上を掲げました。
OECDは現在、Future of Education and Skill 2030のフェーズ2(ティーチング・コンパス2030)として加盟国のカリキュラム改定、
それと連動した教授法・評価法や教員養成・教員研修改善などへの支援に取り組んでいます。
日本でも「ウェルビーイングの向上」を掲げた第4次教育振興基本計画(2023年閣議決定)に大きな影響を与えました。
今般、ラーニング・コンパス2030の取りまとめ責任者であり、フェーズ2で世界中を飛び回る田熊美保氏(OECD教育・スキル局)を講師にお迎えし、
ラーニング・コンパス2030の核心部分について深く伺い、日本における今後の消費者市民教育のあり方について議論する機会にできればと考えております。
議論を深めるため、参加ができない方も含めて事前に質問をお送りください。
2024年度 関東支部例会
日程:6月9日(日)記念誌関連イベント・第1回研究発表会
6月22日(土)第2回研究発表会
場所・開催方法:
6月9日(日)
明海大学 浦安キャンパス (JR「新浦安駅」徒歩約8分)
6月24日(土)
Zoomによるオンライン開催
内容:
6月9日(日)14:00~17:10
◎記念誌関連イベント 14:00~15:30
テーマ:消費者教育の新しい動向
関東支部の設立40周年となる2022年度には
「消費者教育推進法成立から10年:何が変わり、何が変わっていないのか?―今後の展望に向けて―」と題したリレートークが開催されました。
次年度には「生活政策と消費者教育―生活者のための政策論」について討論する機会を経て、
昨年は「新しい学習指導要領にもとづく家庭科・公民科と消費者教育」と
「消費者教育に求められる金融のリテラシーとウェルビーイングの視点」をテーマに講師を招いた講演会を開催しました。
関東支部の40周年を契機とした一連の支部活動を振り返ることを目的として、下記の3部から構成される記念誌をまとめているところです。
<日本消費者教育学会 関東支部 40周年記念誌「消費者教育の新しい動向」>
第1部 消費者教育推進法成立から10年:これまでの動向と今後の展望
第2部 新しい学習指導要領にもとづく家庭科・公民科と消費者教育
第3部 消費者教育に求められる金融のリテラシーとウェルビーイングの視点
◎第1回研究発表会 15:40~17:10
座長:山岡義卓(神奈川大学)
1.高橋義明(明海大学)・櫻庭卓人(明海大学 学部生)
食糧危機下での昆虫食―消費者教育は貢献するか
2.?原智美(東京学芸大学附属高等学校・東京農工大学大学院 院生)
金融教育における外部講師の効果とその可能性
3.小林知子・庄司佳子・奥西麻衣子・河原佑香(公益財団法人消費者教育支援センター)・柿野成美(法政大学大学院)
地域の連携・協働による消費者教育の可能性―近江八幡市のこども中心の取組から―
6月22日(土)14:00~14:30
第2回 研究発表会
座長:小野由美子(東京家政学院大学)
4.勝又淳司(日本女子大学家政学部)
大学生に対する適正飲酒推進に向けた研究 -授業プログラムの開発と効果検証を中心として-
2024年度 関東支部総会・シンポジウム
日程:2023年12月3日(日)・支部総会 17:15~17:45 ※入室開始17:05
・講演会 18:00~19:30
形式:支部会員を対象にしたZoomによるオンライン開催
講演:
<テーマ> 金融のリテラシーとウェルビーイング
―エストニア共和国とEU諸国の研究動向を中心に―
<講師>
Leonore Riitsalu(レオノーラ リッツアロウ)氏
エストニア ビジネス スクール及びタルトゥ大学 客員講師
2023年度 関東支部例会
日程:6月4日(日)講演会・第1回研究発表会 ※講演会は一般無料公開
6月24日(土)第2回研究発表会
場所:
6月4日(日)
法政大学大学院政策創造研究科 新一口坂校舎 3階 302教室(JR・地下鉄「市ヶ谷駅」)
6月24日(土)
城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス 1号棟 3階 1301教室(東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩3分)
内容:
〇6月4日(日)14:10~17:10
講演会 14:10~15:30
テーマ:新しい学習指導要領にもとづく家庭科・公民科と消費者教育
講師:丸山 智彰 氏(東京大学教育学部附属中等教育学校)
宮崎 三喜男 氏(都立田園調布高校)
進行:石島 恵美子 氏(茨城大学)
講師紹介:樋口 雅夫 氏(玉川大学)・小野 由美子 氏(東京家政学院大学)
<概要>
中学校では令和3年度から、高校では令和4年度から新しい学習指導要領による家庭科と公民科の教科書が使われています。
今回は学校現場からの問題提起を受けて、会員相互で課題解決のための意見交換を実施します。
支部会員には中学校や高校の教諭に加え、検定教科書の執筆者も在籍しており、行政や業界団体の立場で活動する会員もいます。
40周年記念事業として、12月に開催の講演会にも続く形で消費者主体の消費者教育や金融教育についての議論を重ね、関東支部としての提案を発信してまいりましょう。
第1回研究発表会 15:40~17:10
座長:中村年春(元大東文化大学)
1.柿野成美(法政大学大学院)・奥西麻衣子(消費者教育支援センター)・ 河原佑香(消費者教育支援センター)・小林知子(消費者教育支援センター)・庄司佳子(消費者教育支援センター)
消費者教育コーディネーターの在り方に関する研究―当事者を対象とした調査結果を中心に―
2.小関隆志(明治大学経営学部)
来日前の労働者への金融教育
3.田中義雄(昭和女子大学大学院生活機構研究科)
企業人のための「シン・消費者教育」のススメ―共創社会実現に向けた新入社員教育の実践的アプローチ―
〇6月24日(土)14:00~17:20
第2回 研究発表会
座長:神山久美(山梨大学)
1.山岡義卓(神奈川大学)
CSA(Community Supported Agriculture)様農業体験プログラムが食品消費に及ぼす影響
―都市近郊における米作り体験活動に基づく考察―
2.杉本一生(千葉大学大学院教育学研究科)・齋藤美重子(川村学園女子大学)
総合を中核とした教科等横断的な消費者教育の検討~食品ロスを題材にして~
3.石島恵美子(茨城大学)・松葉口玲子(横浜国立大学)
地域課題「干し芋残渣の廃棄問題」に対する中学生の課題意識と問題解決意識についての考察
座長:中川壮一(消費者庁)
4.藤脇智恵子(第一生命保険株式会社)
企業による消費者教育・金融保険教育の実践~人生100年時代、高校における金融教育必須化への対応~
5.小野由美子(東京家政学院大学)
要支援消者に対する家計管理支援のあり方―知的障害や精神障害のある利用者の日常的な金銭管理を中心に―
6.丸山智彰(東京大学教育学部附属中等教育学校)
動画制作活動を取り入れた高校家庭科の消費者教育―主体的・対話的で深い学びを目指して―
2023年度 関東支部総会・シンポジウムのご案内
日程:2022年12月4日(日)会場:東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス 5階 1508教室
・受付開始:14:10~
・パネルディスカッション(一般公開無料):14:30~16:00
・関東支部総会:16:15~17:15
参加を希望される方は12月2日(金)までにこちらのフォームから申込みをしてください。
〇パネルディスカッション
<テーマ> 生活政策と消費者教育―生活者のための政策論
<問題提起>
上村 協子 氏(東京家政学院大学)
<パネリスト>
佐々木 俊治 氏(文部科学省)
樋口 雅夫 氏(玉川大学)
中川 壮一 氏(消費者庁)
<概要>
日本の消費者教育を、生活政策へと拓くためには何がポイントになるのでしょうか。
「生活政策とは生活を対象とした政策ではなく、生活者のための政策論である」と
『御船美智子論文集』第?章生活政策で色川卓男氏は提示しました。
同書の第?章消費者教育(磯村浩子氏担当)や、第?章家計管理論から「家計組織・家計組織化」研究へ(重川純子氏)からも読み取れるように、
日本の消費者教育は、家計簿記帳やコミュニティでの相談など、家計・地域の暮らし研究を基軸に生活文化も視野に展開してきた特徴をもちます。
急速なデジタル化の進展や若い世代の動き、トップダウンではなくボトムアップの消費者教育へ、生活創造が求められています。
前年度の関東支部役員によるリレートークも参考に意見交換を行います。
2022年度文部科学省消費者教育フェスタ(岐阜・東京・浜松)を支えるパネリストによる、
ディスカッションでは会場の皆さんからの積極的なご発言も歓迎いたします。
2022年度 関東支部例会のご案内
日程:6月11日(土)講演会(リレートーク)・第1回研究発表会 ※講演会は一般無料公開
6月26日(日)第2回研究発表会
方法:
6月11日(土)対面による開催
城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス1号棟 3階 1301教室
東京都千代田区紀尾井町3-26 (東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口より徒歩3分)
6月26日(日)Zoomによるオンライン開催
内容:
〇6月11日(土)14:10~16:40
講演会(リレートーク第2弾) 14:10~15:30
テーマ:消費者教育推進法成立から10 年:何が変わり、何が変わっていないのか? -今後の展望に向けて- 話題提供者:関東支部役員によるリレートークおよび参加者間の情報交流
<概要> 消費者教育推進法が成立して早くも 10 年が経過しましたが、この間、消費者教育に携わる私たちにとって、どのような変化が起きたでしょうか?
何が変わり、何が変わっていないのか。
このことを振り返ることによって、今後の消費者教育の展望を切り開くきっかけ作りとしたいと考え、前回12月に続いて関東支部役員によるリレートーク第2弾を実施します。
<話題提供・関東支部役員紹介(苗字のみ・50 音順)>
阿部、天野、上村、小野、神山、柿野、佐藤、高橋、土田、角田、樋口、中川、中村、中原、西村、松葉口、山岡
*今回は上記役員のうち前回登壇者以外の登壇を予定。
第1回研究発表会 15:40~16:40
座長:樋口雅夫(玉川大学)
1.齋藤美重子(川村学園女子大学)・齋藤和可子(中央大学附属中学校・高等学校)
高等学校「家庭」と「公共」との金融教育クロスカリキュラムからエシカル消費への展開
2.池垣陽子(埼玉県立蓮田松嶺高等学校)
不当表示広告調査を用いた社会参加意識を促す授業開発
〇6月26日(日)14:00~16:30(13:40から入場開始)
第2回 研究発表会
座長:上村協子(東京家政学院大学)
1.神山久美(山梨大学)
消費生活コンサルタントのライフヒストリー
2.石島恵美子(茨城大学)・松葉口玲子(横浜国立大学)
消費者市民の視点を育むフェアトレードに関する調理実習プログラムの検討
3.小野由美子(東京家政学院大学)・柿野成美(法政大学大学院)・川崎孝明(筑紫女学園大学)・上杉めぐみ(愛知大学)
キャッシュレス決済の普及に伴う高校生を対象とした消費者教育に関する研究
座長:天野晴子(日本女子大学)
4.柿野成美(法政大学大学院)
地方自治体における学校消費者教育の実施に向けた連携・協働に関する研究
5.庄司佳子・小林知子・奥西麻衣子・河原佑香(公益財団法人消費者教育支援センター)・柿野成美(法政大学大学院)
18歳成人に求められる消費者教育のあり方について―2021年度「高校生の消費生活と生活設計に関する調査」結果から
2022年度 関東支部総会・講演会(リレートーク)
日程:2021年12月19日(日)14:30〜16:00方法:Zoomによるオンライン開催
〇リレートーク
テーマ:消費者教育推進法成立から10年:何が変わり、何が変わっていないのか?−今後の展望に向けて−
話題提供者:関東支部役員によるリレートークおよび参加者間の情報交流
概要:消費者教育推進法が成立して早くも10年が経過しましたが、この間、消費者教育に携わる私たちにとって、どのような変化が起きたでしょうか?
何が変わり、何が変わっていないのか。このことを振り返ることによって、今後の消費者教育の展望を切り開くきっっかけ作りとしたいと考え、関東支部役員によるリレートークを実施しました。
2021年度関東支部例会(オンライン開催)
<第1回>2021年6月12日(土)講演会・第1回研究発表会
〇講演会 14:15〜15:45
演題:「消費者市民社会の実現におけるライフサイクルの考え方の必要性」
講師:松本真哉氏(横浜国立大学大学院環境情報研究院教授、横浜市地球温暖化対策推進協議会 会長)
○第1回研究発表会 16:00〜17:00
座長:天野晴子(日本女子大学)
1.高橋勝也(名古屋経済大学)
高校生の消費行動に対する意識と教材開発に向けた課題と展望
2.尾崎裕子・北島孝紀(消費者庁)
インターネット利用における消費者意識・行動の変化
<第2回>
2021年6月26日(土)第2回研究発表会 13:00〜16:45
座長:上村協子(東京家政学院大学)
1.神山久美(山梨大学)
1970年代の企業への教育活動-一般財団法人日本消費者協会「コンシューマー・オフィサー養成講座」の意義-
2.石島恵美子(茨城大学)・豊田悠夏(城里町立桂小学校)・松葉口玲子(横浜国立大学)
小学校における食品ロス学習の新たな可能性と課題
3.野中美津枝(茨城大学教育学部)
消費者教育におけるパフォーマンス課題を取り入れた協調的問題解決学習の効果
座長:山岡義卓(神奈川大学)
4.沼田夫佐与(日本女子大学大学院人間生活研究科・院生)・天野晴子(日本女子大学)
シェアリングエコノミーの広がりと消費者教育の可能性
5.山本輝太郎(明治大学)
疑似科学的広告における「体験談型」強調表示の問題要因分析
2021年度関東支部総会・講演会
日 程:2020年12月13日(日)方 法:Zoomによるオンライン開催
講演会:14時30分〜16時00分
演 題:「消費者行動が新型ウイルス発生に歯止め?
―コンゴ共和国における FSC認証林業事業者による森林保全と人権配慮の実例」
講 師:西原 智昭 氏(星槎大学共生科学部 特任教授)
2020年度関東支部例会
2020年6月13日と27日に開催予定だった例会は中止となりました。(報告予定者にはその内容を提出頂き、承認されたものは報告されたことと致しました)
2020年度関東支部総会・講演会
日 程:2019年12月15日(日)場 所:東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス 1508室
講演会:13時30分〜15時00分
演 題:これからの消費者教育―DESDの経験を活かし、SDGsの本質に向き合う
講 師:佐藤 真久 氏(東京都市大学 環境情報学研究科 教授)
2019年度関東支部例会
<第1回>2019年6月8日(土)講演会・第1回研究発表会
東京家政学院大学千代田三番町キャンパス 1508教室
13:00〜14:00(受付開始12:30) 講演会
講演者 市毛祐子氏(文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官)
演 題 「高等学校家庭科における消費者教育〜新学習指導要領の実施に向けて〜」
14:00〜14:30 市毛祐子氏を囲んで参加者との意見交換会(懇親会)
15:00〜16:00 第1回研究発表会
座長:天野晴子(日本女子大学)
1.小野由美子(東京家政学院大学)・上杉めぐみ(愛知大学)
キャッシュレス決済の推進に伴う消費者教育のあり方について
―韓国消費者院へのヒアリング及び日本の高校生への意識調査等の分析を通して―
2.神山久美(山梨大学)
教職大学院における消費者教育の可能性
<第2回>
2019年6月22日(土)第2回研究発表会
城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス 1号棟 3階1301教室
13:00〜16:45 第2回研究発表会
座長:大竹美登利(元東京学芸大学)
1.山本輝太郎(明治大学情報コミュニケーション研究科(院生))
牛乳と健康に関する消費者の認識―牛乳有害説に着目して―
2.石島恵美子(茨城大学)
家庭内の食品ロスの実態と関連要因
座長:阿部信太郎(城西国際大学)
3.?橋勝也(名古屋経済大学法学部)
地歴・公民科教員の消費に対する意識から考察する経済教育
4.中川壮一(公益財団法人消費者教育支援センター)
消費者教育の体系イメージマップの活用と課題について
座長:柿野成美(公益財団法人消費者教育支援センター)
5.荒井きよみ(東京都立戸山高等学校)
SDGsの視点による実践的体験的学習における知の検討
6.釘宮悦子(NACS消費生活研究所)
消費生活サポーターの活動に関する一考察(仮)
7.柿沼由佳(公益社団法人全国消費生活相談員協会消費者教育研究所)
アクティブシニアの情報通信環境による消費行動
2019年度関東支部総会・講演会
日 程:2018年12月15日(土)
場 所:日本女子大学目白キャンパス 百年館低層棟1階104教室
講演会:13時30分〜15時00分
演 題:SDGsと消費者教育―誰ひとり置き去りにしない消費者教育とは―
講 師:中原 秀樹 氏(東京都市大学名誉教授)
2018年度関東支部例会
<第1回>2018年6月2日(土)講演会・第1回研究発表会
東京家政学院大学千代田三番町キャンパス 1303教室
13:00〜14:20 講演会(受付開始12:30)
講演者:独立行政法人国民生活センター理事長 松本恒雄氏
題名:「成年年齢の引き下げ問題と消費者教育」
講演資料はこちらから
14:30〜15:00 松本恒雄氏を囲んで参加者との懇親会(意見交換)
司会:角田真理子氏(明治学院大学)
※講演会・懇親会(意見交換会)は、どなたでも参加できます(無料・事前申込不要)
15:15〜17:45 第1回研究発表会
座長:天野晴子(日本女子大学)
1.荒井きよみ(東京都立戸山高等学校)
「高校生の実践的な学びによるSDGsの可能性」
2.宮川有希(横浜国立大学大学院)、上村協子(東京家政学院大学)、山岡義卓(神奈川大学)、松葉口玲子(横浜国立大学)
「食を学ぶ女子大生の食品ロス削減意識と行動〜SDGsとプロシューマ―教育〜」
座長:小野由美子(東京家政学院大学)
3.山岡義卓(神奈川大学)
「農業体験プログラムの企画・運営に携わることの消費者教育的意義」
4.柿沼由佳(公益社団法人全国消費生活相談員協会 消費者教育研究所)
「成人向け消費者教育の必要性」
5. 齋藤美重子(川村学園女子大学)
「意見再構築力を育成するアサーティブ・ディベート〜成年年齢引き下げは是か非か〜」
<第2回>
2018年6月16日(土)第2回研究発表会
城西国際大学東京紀尾井町キャンパス1号棟 1301教室
13:00〜17:45
座長:松葉口玲子(横浜国立大学)
1.佐藤麻子(東京学芸大学附属大泉小学校(非))・山本紀久子(元茨城大学)
「衣服の取扱い表示に着目した洗たく教材の開発」
2.石島恵美子(茨城大学)
「調理実習で育む消費者市民〜食品ロスに着目して〜」
座長:阿部信太郎(城西国際大学)
3.山本輝太郎(明治大学大学院)・石川幹人(明治大学)
「『科学の方法』を学ぶ授業書の開発・実践〜科学的知見に基づく消費者教育展開に向けて〜」
4.小野隆治(元横浜国立大学大学院)、松葉口玲子(横浜国立大学)、西村隆男(元横浜国立大学)
「市民後見人養成カリキュラムにおける消費者教育的視点の必要性の検討」
座長:神山久美(山梨大学)
5.尾崎裕子(消費者庁)
「子どもの事故防止の効果的な対策とは〜保護者等への意識調査の結果から〜」
6.柿野成美(公益財団法人消費者教育支援センター)
「地方公共団体における消費者教育の専門的人材の課題〜教員の成員性をもつ人材を中心に〜」
7. 加藤絵美(特定非営利活動法人親子消費者教育サポートセンター)
「妊婦の魚食によるメチル水銀摂取に関わる消費者教育について」
座長:大竹美登利(元東京学芸大学)
8.中上直子(椙山女学園大学研究生)
「地域の消費者教育の担い手に関する研究〜杉並区消費生活サポーターへの調査を中心に〜」
9.神山久美(山梨大学)
「1枚ポートフォリオ評価(OPPA)を用いた消費者教育の実践」
2018年度関東支部創立35周年記念事業
消費者教育推進法施行5周年記念
シンポジウム・記念パーティ
関東支部は1982年10月に活動を開始し本年で35周年を迎えました。その記念事業として、「消費者教育推進法施行5周年記念シンポジウム」及び「記念パーティ」を開催いたしました。
<シンポジウム>
・日時:2017年12月10日(日)13:50〜16:40
・場所:日本女子大学目白キャンパス百年館低層棟505教室
・案内チラシは <こちら>
<記念パーティ>
・日時:2017年12月10日(日)17:30〜19:30(受付開始17:00)
・場所:ホテル椿山荘東京 椿山荘プラザ棟1階カシオペア (東京都文京区関口2-10-8)
2017年度関東支部例会
<第1回 6月3日(土)> 大東文化会館・13:00〜14:30 講演会(一般公開)
演題:公益通報者保護法の改正について
講師:読売新聞大阪本社 井手裕彦氏
・14:45〜 研究発表会
1.田村 徳至(信州大学)
「金融経済分野を中心とする消費者教育に関する一考察
〜長野県小・中・高教師に対する予備調査の分析結果に着目して〜」
2.末川 和代(日本女子大学大学院:院生)・天野 晴子(日本女子大学)
「中学校家庭科消費生活領域における防災学習の検討
〜東日本大震災以降の災害関連消費者問題及び防災ブックレット等の分析を通して〜」
3.柿沼 由佳(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会消費生活研究所)
「消費生活相談員が実施する消費者教育の現状と課題
〜高校生・教師のアンケート調査から〜」
4.中川 壮一(公益財団法人消費者教育支援センター)
「子育て世代向け金融教育プログラムの考察
〜沖縄における『くらしとお金の教室』を事例として〜」
5.松葉口 玲子(横浜国立大学)
「学校教育における消費者教育の新たな可能性」
<第2回 6月17日(土)> 城西国際大学紀尾井町キャンパス
13:00〜 研究発表会
1.佐藤 麻子(東京学芸大学附属大泉小学校(非))・山本 紀久子(元茨城大学)
「教員養成における繊維製品のラベル作りを取り入れた授業実践」
2.野中 美津枝(茨城大学)、高? 昌己(茨城大学教育学部附属中学校)
「消費者市民を育成する『すごろく』の開発と授業実践」
3.釘宮 悦子(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会消費生活研究所)
「消費生活サポーター養成講座に関する一考察」
4.佐藤 俊恵(法政大学大学院:院生)
「消費生活相談員が消費者救済に果たしてきた役割」
5.八代田 道子(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)
「格差社会における消費者問題の考察」
6.山本 輝太郎(明治大学情報コミュニケーション研究科:院生)
「消費者の科学リテラシー育成に向けた疑似科学的言説の活用」
7.小野 由美子(東京家政学院大学)・川崎 孝明(尚絅大学短期大学部)
「全国の特別支援学校における金銭管理教育と社会資源の活用について」
8.神山 久美(山梨大学)
「大学初年次における消費者教育の実践と評価の試み」
2017年度関東支部総会・講演会
2016年12月10日(土) 於:大東文化会館 4階K401・402研修室〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-4-21 TEL 03-5399-7399
受付開始:13時30分
講演会:14時00分〜15時30分(一般公開)
関東支部総会:15時45分〜16時45分
★講演会★
演 題:肉・卵・ミルクはエシカルな生産と消費へ
講 師:岡田 千尋 氏(NPO法人アニマルライツセンター代表理事)
講演資料はこちら(岡田様のご厚意で公開します)
<講演概要>
毎日、口にする肉や卵、ミルク、その生産に使われる動物への配慮が今の日本でどのように行われ、また行われていないのか。ケージフリー卵に移行する企業が急増し、180兆円を運用する機関投資企業が動物福祉への取り組みを宣言するなど、消費者、企業、投資家、行政を巻き込んで大きな流れになってきた世界の畜産動物の福祉の取り組みの状況と、そこから遅れを取っている日本の状況の違いとその理由をお話します。
<講師のご紹介>
NPO法人アニマルライツセンターで調査、キャンペーン、戦略立案などを担い、2003年から代表理事を務める。日本全国のアニマルライツの行動ネットワークづくりや、衣類や食品、娯楽のために利用されている動物を守る活動を行い、2005年から開始した毛皮反対キャンペーンでは、10年間で日本の毛皮消費量を78%減少させてきた。現在特に日本で知られていない畜産動物の現状の調査、及び解決に向けた提言や啓発への動きを強めている。また、ヴィーガンエシカルマガジンサイトHachidoryの運営も行う。
2016年度関東支部総会・講演会
2015年12月5日(土) 於:主婦会館プラザエフ 5階会議室(JR線「四ッ谷駅」麹町口 徒歩1分 東京都千代田区6番町15)
受付開始:13時00分
講演会:13時30分〜15時30分(一般公開)
支部総会:15時45分〜16時45分(支部会員のみ)
★講演会★
「健康食品」で健康が買えますか?「健康食品」類の問題性を考える
〜保健機能食品(トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品)と「健康食品」〜
講演資料はこちら(高橋先生のご厚意で公開します)
講 師:高橋久仁子先生(群馬大学教育学部名誉教授)
後 援:一般社団法人全国消費者団体連絡会
<講師からのコメント>
何らかの保健効果を期待し、経口摂取する製品が「健康食品」です。医薬品を連想させる錠剤やカプセル状の製品を「サプリメント」と呼ぶ風潮もありますが、すべて含めて「健康食品」です。「健康食品」の"有益性"に関する情報は科学的根拠の有無に関わらず産業界や宣伝広告を含めメディアから大量に提供されていますが、"有害性"に関する情報は乏しいのが現状です。トクホや機能性表示食品を含めた「健康食品」類の問題性について考えたいと思います。
<講師のご紹介>
日本女子大家政学部食物学科管理栄養士専攻後、同大学院家政学研究科食物・栄養学専攻修士課程修了。その後、東北大学大学院農学研究科食糧科学専攻 博士課程修了(農学博士)。群馬大学教育学部教授を歴任。2014年同大学名誉教授。健全な食生活の営みを阻害する要因のうち、フードファディズムとジェンダーに着目し、研究。フードファディズムとジェンダーを超えた「メディアに惑わされない食生活」を提唱している。著書に、著書に、『フードファディズム:メディアに惑わされない食生活』中央法規出版(2007)、『「食べもの神話」の落とし穴:巷にはびこるフードファディズム』講談社ブルーバックス(2003)、その他多数。
★支部総会★
議 題
1.2015年度 活動報告について
2.2015年度 決算報告について
3.2016年度 活動計画案について
4.2016年度 予算案について
5.関東支部会則改正について
6.その他
*支部会則改定が議題になっています。改定案はこちら
2015年度日本消費者教育学会関東支部例会
<第1回 5月23日(土)> 城西国際大学紀尾井町キャンパス1号館3階301教室〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26。東京メトロ有楽町線麹町駅1番出口より徒歩3分 あるいは、東京メトロ半蔵門線・南北線永田町駅9番出口より徒歩5分。
講演会:13:00〜14:30
「日本の消費者運動を語る:消費者運動の過去・現在・未来」
清水鳩子さん(主婦会館館長・元主婦連合会会長)
消費者庁・消費者委員会ができ、悲願であった消費者教育推進法も制定され、消費者政策の進展は見られるものの、消費者運動・消費者団体の現状と未来について心配する声は多くあります。
日本の消費者運動の草分け的存在である主婦連合会で長年活躍し、同会長を1995年から4年間務めた清水鳩子さんをお招きし、日本の消費者運動の歴史、現状に触れながら未来について語っていただきます。
消費者庁・消費者委員会ができ、悲願であった消費者教育推進法も制定され、消費者政策の進展は見られるものの、消費者運動・消費者団体の現状と未来について心配する声は多くあります。
日本の消費者運動の草分け的存在である主婦連合会で長年活躍し、同会長を1995年から4年間務めた清水鳩子さんをお招きし、日本の消費者運動の歴史、現状に触れながら未来について語っていただきます。
研究発表会14:45〜15:45(2発表)
1.松葉口玲子(横浜国立大学)、本間理絵(東京学芸大学大学院/NHK出版)、シュレスタ・マニタ(東京学芸大学大学院)
「『新しい能力』と消費者市民」
2.野中美津枝(茨城大学)
「小学生の消費生活課題解決能力を育成する授業デザイン」
<第2回 6月20日(土)> 東京家政学院大学千代田三番町キャンパス1706教室
〒102-8341 東京都千代田区三番町22番地。JR中央線・総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営地下鉄新宿線の市ヶ谷駅から徒歩約8分(地下鉄 A3番出口)。
研究発表会 13:00〜17:15(8発表)
(13:00〜15:00)
1.廣田 浩一(山の手総合研究所)・小野由美子(東京家政学院大学)・斎藤滋(桐光学園小学校)
「小学校の知的財産教育における授業内容と感想文の分析」
2.土田あつ子(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)
「住宅に関する消費者啓発に向けた新たな考察(2)」
3.?原智美(東京学芸大学附属世田谷中学校)・佐藤麻子(東京学芸大学附属小金井中学校)・山本紀久子(茨城大学名誉教授)
「消費者安全を取り入れた家庭科教材の開発」
4.志村結美(山梨大学)・野村千佳子(山梨学院大学)
「大学生と親世代の消費者教育に関する認識」
(休憩15分)
(15:15〜17:15)
5.山岡義卓(神奈川大学)
「都市近郊の農家が実施する農業体験プログラムの消費者教育としての可能性」
6.小野由美子(東京家政学院大学)
「特別支援学校における家計管理に関わる教育支援の現状と課題」
7.神山久美(山梨大学)
「学校での消費者教育に携わる人材の育成:独立行政法人国民生活センターの研修調査」
8.柿野成美(公益財団法人消費者教育支援センター)
「地方自治体における消費者教育の専門的人材の実態と課題」
2015年度日本消費者教育学会関東支部講演会
日 時:12月20日(土)14時30分〜16時30分場 所:日本女子大学目白キャンパス百年館低層棟101教室
「水文学と消費者」
講 師:東京大学生産技術研究所教授 沖大幹 先生
水文学(すいもんがく、英語: hydrology)とは、地球上の水循環を対象とする地球科学の一分野であり、主として、陸地における水をその循環過程より、地域的な水のあり方・分布・移動・水収支等に主眼をおいて研究する科学です。研究対象は、水の供給源としての降水の地域的・時間的分布特性、蒸発、浸透、陸水や地下水の移動等が中心です。
(講演会はどなたでも無料で参加できます。事前登録不要)
2014年度日本消費者教育学会関東支部講演・研究発表会
<第1回5月31日(土)> 城西国際大学紀尾井町キャンパス301教室?. 講演会:井田徹治氏「フクシマと消費者・市民」(14:00〜15:30)
企画主旨:原発再稼働の大合唱のなかでフクシマを絶対に忘れてはならないと考えます。また国家機密保護法で情報隠しが行われようとしている今、消費者・市民は何をすべきかについて本支部としても考えるべき問題です。共同通信社編集委員・論説委員として環境・エネルギー・開発問題を担当され多くの関連の国際会議も取材されている井田徹治さんに講演をいただきます。市民科学と市民社会の重要性などの話にも触れていただけるとのことです。
講師プロフィール:共同通信社編集委員・論説委員(環境・エネルギー・開発問題担当)。1959年生まれ。1983年東京大学文学部卒業、共同通信社に入社。2001年から2004年、ワシントン支局特派員(科学担当)。環境と開発の問題を長く取材、気候変動に関する政府間パネル総会、ワシントン条約締約国会議、環境・開発サミット(ヨハネスブルク)、国際捕鯨委員会総会など多くの国際会議も取材している。著書に『サバがトロより高くなる日 危機に立つ世界の漁業資源』(講談社現代新書)、『ウナギ 地球環境を語る魚』(岩波新書)、『生物多様性とは何か』(岩波新書)など。
?.研究発表会(15:45〜17:15) 発表3組(1組30分)
1.消費者市民育成をめざした金融リテラシー教育の効果検証
橋長真紀子(長岡大学)・西村隆男(横浜国立大学)
2.消費者教育推進における学校、教育委員会、消費者行政の連携の可能性
大野田良子(日本女子大学大学院)・天野晴子(日本女子大学)・柿野成美(公益財団法人消費者教育支援センター)
3.社会参画意識を高める消費者市民教育〜高等学校家庭科実践より〜
石島恵美子(茨城大学)・橋長真紀子(長岡大学)

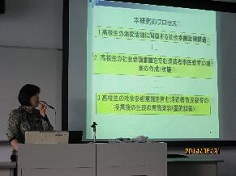
<第2回6月28日(土)>日本女子大学百年館305教室>
研究発表会 13:00〜17:15:8組(1組30分)
(13:00〜15:00)
1.住宅に関する消費者啓発に向けた新たな考察〜「住宅すごろく」の上がりに対する考察〜
土田あつ子(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)
2.省エネ行動にむけた教育の現状と課題
松葉口玲子(横浜国立大学)
3.風評被害の実像〜消費者教育と産地選好〜
高橋義明(筑波大学)
4.家庭科室を活用した消費者安全教育
佐藤麻子(東京学芸大学附属小金井中学校)・山本紀久子(茨城大学名誉教授)
(休憩15分)
(15:15〜17:15)
5.消費者教育推進法施行1年目にみる地方公共団体のアプローチ〜政令市を中心に〜
柿野成美(公益財団法人消費者教育支援センター)・大野田良子(日本女子大学大学院)
6.消費者教育推進法施行後の消費者政策〜山梨県の事例〜
神山久美(山梨大学大学院)
7.「地産地消」をテーマとした企業との連携によるプロジェクト型授業の学習効果について
山岡義卓(神奈川大学)・小野由美子(東京家政学院大学)・上村協子(東京家政学院大学)
8.全国消費生活相談情報にみる心身障害者関連の判断不十分者契約
小野由美子(東京家政学院大学)
2014年度関東支部総会・記念シンポジウム
〜消費者教育推進のための方向性を考える〜
消費者教育推進法施行1年を会員のリレートークで振り返り、今後の推進のための方向性を考える意見交換の場を企画いたしました。日 時:2013年12月14日(土) 14時00分〜16時30分 (受付13時45分〜)
場 所:東京家政学院大学千代田三番町キャンパス1407教室
内容:会員によるリレートーク及びフロアーとのディスカッション
1.学会の果たすべき役割 西村 隆男(横浜国立大学)
2.地方消費者行政推進の視点から 柿野 成美(消費者教育支援センター)
3.教員養成の視点から 神山 久美(山梨大学大学院)
4.市民セクターの視点から 中村 年春(大東文化大学)
5.企業・事業者団体の視点から 山下 俊章(第一生命保険株式会社・ACAP正会員)
<司会・進行> 細川 幸一(日本女子大学)


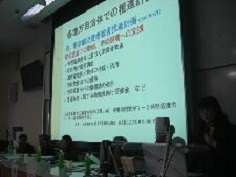
2013年度日本消費者教育学会関東支部講演・研究発表会
第1回: 6月8日(土) (城西国際大学紀尾井町キャンパス302教室)★講演会「倫理的消費」を考える (13時30分〜15時30分)★
? 「倫理的消費」山本良一先生(東京大学名誉教授、IGPN会長)
? 「壊れ易く創る:グリーンウォッシュと倫理的購入」中原秀樹先生(関東支部会員、東京都市大学教授、グリーン購入ネットワーク名誉会長)
★研究発表会 (15時45分〜16時45分)★
? 「持続可能な社会に求められる教養教育の開発―大学生の金融力および消費者市民力に関する調査より―」
橋長真紀子(東京学芸大学大学院連合学校)・西村隆男(横浜国立大学)
? 「利用中の製品の危険情報をどのように伝えるべきか −事故を防止するための消費者の意識改革について−」
越山健彦(千葉工業大学)
第2回:7月6日(土)(日本女子大学目白キャンパス百年館503教室)
★調査結果の報告(13時00分〜13時30分) ★
日本消費者教育学会関東支部・ACAP合同調査「企業における消費者啓発・教育活動に関する実態調査」
(鈴木深雪会員・高橋明子会員・八代田道子会員)
★研究発表会 (13時30分〜17時15分)★
? 「小学校における知的財産教育 ―消費者教育の視点を取り入れた検討―」
廣田浩一(山の手総合研究所)・宮野一大(山の手総合研究所)・小野由美子(東京家政学院大学)・斎藤滋(桐光学園小学校)
? 「中学校技術・家庭科における注意を促すマークの分析」
佐藤麻子(東京学芸大学附属小金井中学校)・山本紀久子(帝京短期大学)
? 「高校生と携帯電話」
中谷ゆう子(明星学園高等学校)
? 「高等学校家庭科における消費者教育の課題 −全国実態調査の分析を踏まえて−」
柿野成美(消費者教育支援センター)
? 「全日制普通科高校で考える『消費者教育』の展開―教科外活動、サークル活動の具体的実践を通して ―」
梶ヶ谷穣(神奈川県立海老名高校)
? 「大学におけるアクティブ・ラーニング:消費者行政との協働」
神山久美(山梨大学大学院)
? 「効率・公正の問題と消費者教育」
阿部信太郎(城西国際大学)

2013年度関東支部総会・記念シンポジウム
場 所 日本女子大学目白キャンパス 百年館低層棟505教室日 時 2012年12月8日(土)13時00分〜16時00分
支 部 総 会 :13時00分〜13時45分
シンポジウム:「原発消費者の責任と権利を考える」 14時00分〜16時00分
企画趣旨:東日本大震災により原発放射能漏れ被害が現実のものとなり、安全面でも経済面でも多大な被害を受けています。一方、原子力発電による電気を我々は購入し、生活してきた「原発消費者」でもあります。原発を選んできた責任として、消費者は事故処理に対する応分の負担をすべきという意見もありますし、一方で、東電しか選べなかった消費者に責任はないとの意見もあります。将来についても原発再稼動の可否が大きな争点になっております。ここでは、原発立地の政治プロセス、地域経済への影響など長年研究してこられた秋元健治教授にご講演をいただき、その後、参加者議論を深めたいと思います。
?講演:原発はどのように推進されてきたか〜原発消費者の視点から〜
日本女子大学家政学部家政経済学科教授秋元健治氏
講師経歴:青森県弘前市出身 早稲田大学社会科学部卒業、岩手大学連合大学院農学研究科(農学博士)修了。著書に『むつ小川原開発の経済分析』(創風社)、『核燃料サイクルの闇−イギリス・セラフィールド』、『覇権なきスーパーパワー・アメリカの黄昏』、『原子力事業に正義はあるか−六ヶ所核燃料サイクルの真実』(現代書館)など。
講演趣旨:未曽有の原発事故を経験しても、なお原発にしがみつこうとする人びとは少なくありません。原子力産業界は、国内にはもう造れないから、新興国や途上国への輸出に活路を見出そうと必死です。それは、かつてアメリカが日本に原発を導入した方法とよく似ています。原発輸出は、他国にドラックを売りつけるようなものです。原発が造られ動き出すと、原発依存から抜け出すことは容易ではありません。
この世紀、国や産業界、電力業界、地域社会が原発をすすめてきたのは、エネルギー問題からではないのです。原子力は本質的に危険だからこそ、広範な分野の組織や人びとに多大な利益を与え続けるものなのです。そうしたことを、原子力推進複合体、電力料金設定の仕組みなどからお話しいたします。
?自由討議 秋元教授の講演を踏まえて自由に議論
2012年度関東支部研究発表会
第1回例会 6月2日(土)13 時30 分〜16 時30 分場所:城西国際大学紀尾井町キャンパス3階301教室
<研究発表会> 13 時30 分〜15 時00 分
「科学実験を活用した消費生活講座『くらしの中のアルコール』(2)」
佐藤典子(郡山女子大学)
「警告表示等による消費者への製品事故回避情報の伝達メカニズム」
越山健彦(千葉工業大学)
「6次産業化と食農教育」
上村協子(東京家政学院大学)
休憩 15 分
<情報・意見交換会> 15 時15 分〜16 時30 分
研究発表会終了後、会員間で最新の情報や意見を交換する場を共有したいと思います。個人的に有している情報や、日頃感じていること等を発言していただけると幸いです。
第2 回例会 7月7日(土) 13 時30 分〜17時15分
場所:日本女子大学目白キャンパス百年館(正門を入って右の高層の建物)103教室
<研究発表会>
「大学生の金融教育−日米調査の分析から−」
柿野成美(消費者教育支援センター)・橋長真紀子(アイオワ州立大学)・西村隆男(横浜国立大学)
「家庭科教科書における<安全マーク>の分析」
山本紀久子(茨城大学)・佐藤麻子(東京学芸大学附属小金井中学校)・大友美恵子(大洗町立大貫小学校)
「要支援消費者」の消費者問題と社会的対応 」
小野由美子(横浜国立大学)
「消費者教育は進化したか〜平成19 年度調査との比較」
高橋義明(国際協力機構)
「高校生と消費生活」
中谷ゆう子(明星学園高等学校)
「消費者の市民性を育む家庭科教育における視点」
荒井きよみ(東京都立忍岡高等学校)
2012年度関東支部シンポジウム・総会
場 所 城西国際大学 紀尾井町キャンパス301教室 (千代田区紀尾井町3-26)日 時 2011年12月3日(土)14時00分〜17時20分
シンポジウム:14時00分〜16時30分(詳細については下記参照)
支 部 総 会 :16時40分〜17時20分
<シンポジウム>「消費者教育推進法案」への期待と課題
13時45分 受付開始
14時00分〜14時05分 開 会
14時05分〜15時20分 「『消費者教育推進法案』への期待と課題」
― 環境教育、食育との比較も含めて ―
講師: NHK解説委員 今井 純子 氏
15時30分〜16時00分 「『消費者教育推進法案』へのコメント」
西村 隆男氏(横浜国立大学教授・学会長)
鶴田 敦子氏(聖心女子大学教授)
16時00分〜16時25分 参加者との意見交換
16時25分〜16時30分 閉 会
2011年度関東支部研究発表会
●第1回例会 2011年5月28日(土)13時30分〜場所:城西国際大学紀尾井町キャンパス3階302教室
<研究発表会> 13時30分〜15時30分
「消費生活専門家育成に関わる集団の役割〜公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の事例から〜」
神山久美(名古屋女子大学家政学部家政経済学科)
「企業の信頼感を高める消費者対応とは〜心理学的実験手法を用いて〜」
釘宮悦子(NACS消費生活研究所)
「「要支援消費者」と消費者教育」
小野由美子(東京家政学院大学(非))
「科学実験を活用した消費生活講座「くらしの中のアルコール」」
佐藤典子(郡山女子大学)
<情報・意見交換会> 15時40分〜16時30分
●第2回例会 2011年6月25日(土) 13時30分〜
場所:横浜国立大学教育文化ホール
<研究発表会> 13時30分〜15時30分
「消費者教育教材及び資料提供のあり方の検討」
奥谷めぐみ(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科)
「消費者安全に視点をあてたレシピ作りの教材開発」
山本紀久子(茨城大学)・山田好子(小田原女子短期大学)
「ネパールの内発的発展と環境教育」
シュレスタ・マニタ(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科)
「フランスの多重債務者の生活支援システムについての一考察」
西村隆男(横浜国立大学)
日本消費者教育学会関東支部シンポジウム
リレートーク「私の考える『消費者教育学』」場 所 日本女子大学目白キャンパス百年館低層棟204教室
日 時 2010年12月11日(土)14時00分〜16時00分
企画趣旨:学会が今年30周年を迎えた。会員第一世代は既存の学問に軸足を置きつつ、消費者教育学に関心を持
ってきたと思われるが、第二世代、第三世代が活躍してきている。消費者教育学とは独自の専門領域として存在し得
るものなのか、あるいは複合的な領域なのか・・・それぞれの専門分野を生かして消費者教育学会で活躍している支部
会員のリレートークによって、学会の存在意義を再確認した。
発言者: 教育学領域から :松葉口 玲子 (横浜国立大学)
家政学領域から :木村 静枝 (元・相模女子大学)
経済学領域から :西村 隆男 (横浜国立大学)
法学領域から :鈴木 深雪 (元・日本女子大学)
企業経営領域から :高橋 明子 (元・相模女子大学)
消費者相談領域から:磯村 浩子 (武蔵野学院大学)
司会進行 :細川 幸一 (日本女子大学)
日本消費者教育学会創立30周年記念全国大会が
開催されました
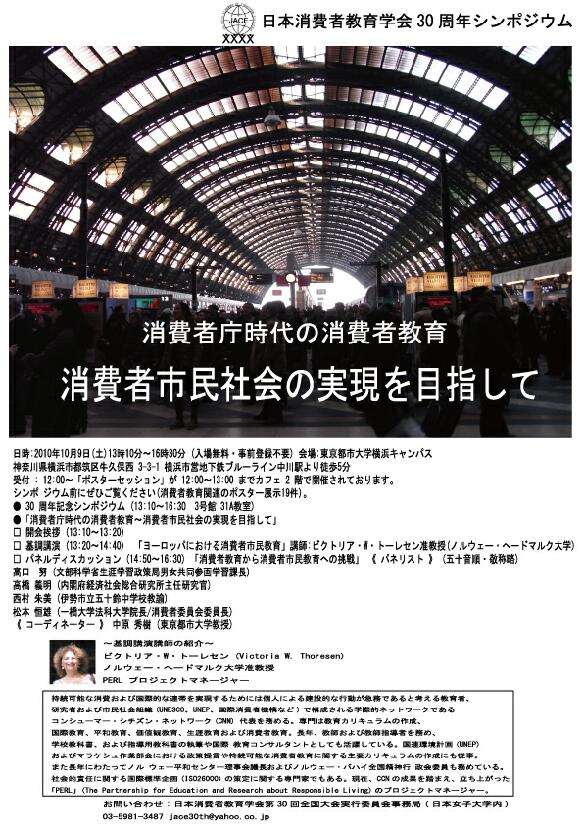


ビクトリア・W・トーレセン博士の基調講演

パネルディスカッション


ハイコ・ステファン博士への感謝状贈呈 韓国消費者連盟・鄭光謨会長への感謝状贈呈


末松義規・内閣府副大臣による祝辞 村井博美・生命保険文化センター理事長による祝辞
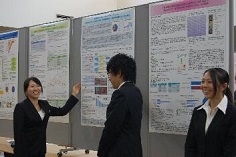

ポスターセッション 研究発表会(2日目・分科会)
2010年度関東支部研究発表会が実施されました
第1回研究発表会 6月5日(土)15時30分〜16時00分場所:日本女子大学目白キャンパス百年館高層棟11階家政経済学科ゼミ会議室
(東京都文京区目白台2−8−1 交通手段:?東京メトロ副都心線雑司が谷駅3番出口から左方向へ徒歩8分、?JR山手線目白駅より都バスで5分あるいは徒歩20分、?東京メトロ有楽町線護国寺駅4番出口徒歩10分)
「消費者のための安全教育コンテンツの開発」
佐藤典子(お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター)
第2回研究発表会 7月10日(土) 13時00分〜16時10分
場所:東京都市大学横浜キャンパス3号館3階
(神奈川県横浜市都筑区牛久保西3-3-1 交通手段:横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅下車徒歩5分)
「消費者教育教材の評価に関する研究」
柿野成美(消費者教育支援センター)、橋長真紀子(消費者教育支援センター)、
長沼有希(消費者教育支援センター)
「消費者教育視点によるフェア・トレードの現状と課題」
シュレスタ・マニタ(横浜国立大学教育学研究科修士課程)、松葉口玲子(横浜国立大学)
「知的障害者を対象にした消費者教育―特別支援学校等での実践から―」
小野由美子(東京家政学院大学(非))・名川勝(筑波大学)・鈴木佳江(聖ヨゼフ学園中高等学校(非))
「消費者教育の動向と若干の論点」
鶴田敦子(聖心女子大学)
「社会科公民科教育と消費者市民」
阿部信太郎(城西国際大学)
「消費者教育の評価のあり方に関する一考察」
神山久美(東京家政学院大学(非))
「多重債務者の生活再建支援におけるインテーク面接の方法」
田村愛架(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程)
「効果的な消費者教育を促す教員支援の方策に関する実践的検証」
奥谷めぐみ(東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程)・西村隆男(横浜国立大学)
「消費者の変化と企業の対応に関する考察」
清水きよみ(社団法人消費者関連専門家会議)
「針山の手順書作りを取り入れた消費者教育の教材開発」
山本紀久子(茨城大学)、山田好子(小田原女子短期大学)


「第171回国会消費者庁関連3法案審議における消費者教育関連政府答弁集」を作成しました
国会での消費者庁設置審議の際に政府よりありました消費者教育関連の答弁を一冊にまとめ、2009年12月5日に発行しました。冊子は衆参消費者問題特別委員会委員長、理事等の国会議員にお送りするとともに、福島消費者行政担当大臣、大島内閣府副大臣、泉内閣府大臣政務官、松本消費者委員会委員長、内田消費者庁長官にもお送りしました。同冊子のPDF版はこちらからダウンロードできます。
シンポジウム 「消費者庁と消費者教育」が開催されました
場 所 日本女子大学目白キャンパス香雪館204教室日 時 2009年12月5日(土)14時00分〜17時00分
第1部 学生が語る消費者教育(14時00分〜15時10分)
国民生活センターで今年8月31日、9月1日の両日に開催された本学会『学生セミナー」に参加した学生4名を交えたディスカッション
パネリスト
横浜国立大学大学院生 シュレスタ マニタ
大阪教育大学大学院生 服部 晃次
立教大学法学部学生 安藤 奏
日本女子大学家政学部学生 丸山 智子
コーディネーター 日本女子大学 細川 幸一
(休憩 10分)
第2部 消費者庁時代の消費者教育を考える(15時20分〜17時00分)
講演? 消費者庁の設立論議における消費者教育
横浜国立大学教授 西村 隆男
講演? 「消費者市民社会」実現のための消費者教育
内閣府経済社会総合研究所主任研究官 高橋 義明
討 議